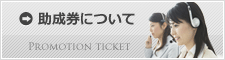Author Archive
ツボのはなし
ツボは全身に360有余あり、内臓の病変の表れる場所でもあります。いわゆるツボ反応と言われるものですがそれは様々な反応があり、例えば痛み、熱い、かゆい、冷え、鈍麻、過敏、痺れ、がさがさ等です。そしてそれらの範囲も小さい点状から500円玉位まであります。それを視覚と指、手掌の感触により感知しそこに鍼灸で刺激を与えるのです。表面に表れた反応は内臓体壁反射ともいい、逆に体表を刺激することで体壁内臓反射となり内臓の異変を調整することにもなるのです。ツボ反応は正常な時には表れず、ツボ反応がないのは健康な状態といえます。内臓が健康な人は皮膚の状態のツヤとか張りがよく、化粧ののりもいいです。そして若々しく見えます。これらのことは大切なことなのです。
手足は何の為にあるか
手足は何の為にあるか?手は物をつかんだり、重いものを持ったり、細かい作業をしたりあらゆる動作に使います。又歩く時のバランスをとるのには重要です。一方足はもちろん歩く為で、時には走ったり、飛んだり、跳ねたりします。手足には経絡の全てが通っています。そして五臓六腑のツボも全てそろっています。つまり手足を使い動かす事は内臓の働きをよくするのです。そして歩くことは大地を踏みつけることになり、振動が骨にひびき骨粗鬆症になりにくいのです。外気を吸って気分を変えれば、又新陳代謝が高まるのではないかと思います。毎日食べているので毎日歩かないとバランスがとれないと思います。
7月臨時休診のお知らせ
臨時休診のお知らせです。7/3(水)7/20(土)は休診となります。みなさまにはご迷惑をおかけしますがご了承のほどよろしくお願い致します。
補と瀉
ツボの反応は虚と実に分けられます。つまり病態の状態が盛んであれば実の反応がツボに現れ、逆に沈んでいれば虚の反応が現れる。実の反応のツボには瀉の刺激をして、盛んになりすぎているエネルギーをとり、沈んでいるツボにはエネルギーを加えて元気にさせる補の治療をします。そうすることによって左右のツボを平の状態になることが正常なのです。毎日がストレスの中にいるとツボも乱れやすく、病になることが多くなります。常にツボをコントロールしておくことが大事かと思います。
病の氣
病が長引くと、氣持ち的に弱気になり、どうしてもマイナス思考になりがちです。そうすればするほど深く病に入り込んで、病そのものを悪化してしまいます。そうではなく病になっても必ず治る、良くなるとあきらめずにいることが先ず大事なことです。そして様々な治療法がありますが、根気よく探しそして治療を継続することです。そうすると、いつかは必ず良い方向に向かっていきます。病気になるのはそれなりの理由が必ずあります。自分の周りの事を振り返って、立ち止まって見る良い機会と考えられれば幸いです。
臨時休診のお知らせ
臨時休診のお知らせです。出張のため5/28(火)~6/3(月)まで休診となります。みなさまには ご迷惑をおかけしますがご了承のほどよろしくお願い致します。
ツボの効用 神門
神門は手首の付け根、小指側の窪んだところにとります。ここは神の門ですから大事なツボです。効能は主に心、精神と関係する働きをするのです。不安感があるとか、眠れないとか、イライラしたり氣持ちに落ち着きがない時には、非常に効果的なツボです。そのほかには便秘とか、脳梗塞の後遺症で話すことができないとかにも効果的です。治療は根気よく継続すればいい方向に向かいますのであきらめないことです。
GW期間中の診療日のお知らせ
GW連休中の診療です。
診療日は4月27日 30日 5月2日(木)
他は暦通りの休日です 。
症例 左肩痛
平成31年3月 40代 女性
左肩をぐるぐる回すと痛い2週間まえより痛くなり、なかなか治らないとの事。以前に右の肩も同じようになり、鍼で治ったので又来院したとの事。診ると左肩の患部の圧痛、左百会後ろ、左天宗、右肝兪1行、左陰谷、左太衝、左侠谿、左肩井、腹部の左肝相火、左上巨虚、他に花粉症ひどく鼻水粘る。仕事は夜勤もある。ツボ反応を見るとストレスによるものと判断し、肝気上昇による痛みと考え、左百会後ろに強刺激の鍼を10分位置鍼、治療後左腕をぐるぐる回してもほとんど痛みはない。その後1週間位はよかったが又再発し来院し、今度は左合谷に強刺激の鍼をすると又痛みはとれた。この症例はまた再発する可能性があるので時々は治療が必要ではないかと思っています。
湿邪と脾
湿邪と脾は太陰湿土で陰気が多いので乾燥を好む。湿気の多い所、梅雨時は脾の運化作用を低下させ体液の調整作用も落ちる。又飲食の不摂生、過食、大酒は湿を多く生産して脾を傷め逆に肝気を上昇させることになる。脾が弱ると全身が重だるくなり、寝起きもすっきりせず考えるのもおっくうになります。脾は後天の元気でもあるので全ての栄養はここから入るので、あらゆる臓器の栄養元になります。非常に重要な臓器なので、ここを常に正常に保つ必要があります。先ずは腹八分、食べ過ぎると負担がかかります。過剰労働はいつかは倒れます。そして運動、基本は歩きです。歩くことは手足を動かし腹筋背筋も使い、呼吸も少し早目になります。つまり全身運動は内臓から末端まで気血が流れるので、心身の状態は良好になります。毎日食べるので毎日歩くのです。
« Older Entries Newer Entries »